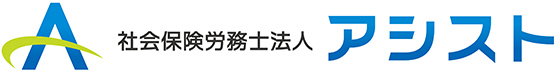法定休日と法定外休日の違いについて
法定休日と法定外休日の違いについて
労働基準法では、使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日(または4週間で4日以上)」を与えることが義務付けられており、これが「法定休日」と呼ばれます。つまり、法律で必ず与えなければならない休日です。一方で、会社が独自に定めている休日(たとえば週に2日のうちのもう1日など)は「法定外休日」となります。こちらは法律上の義務ではなく、会社の就業規則や労使協定などで定められているものです。
この違いは、休日に労働が発生した場合の割増賃金の扱いにも影響します。法定休日に労働させた場合は、35%以上の割増賃金が必要となりますが、法定外休日に労働した場合は、1日の労働時間が8時間を超えない限り、割増賃金の支払い義務はありません(ただし、会社の規定で別途手当を支給する場合もあります)。
ここで重要な点として、法定休日は「暦日(0時から24時までの1日)」として与える必要があるという決まりがあります。つまり、法定休日は1日まるごと休みでなければならず、たとえば「午後から休み」や「深夜0時をまたいで一部だけ休む」といった形では、法定休日として認められません。一方で、法定外休日についてはこのような制限はなく、半日休みや時間単位での休みとして運用することも可能です。
1カ月単位の変形労働時間制を採用する場合について
この制度は、1カ月以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(原則40時間)以内であれば、日ごとの労働時間が8時間を超えてもよいという仕組みです。たとえば、繁忙期には1日10時間働いても、閑散期に労働時間を短く調整することで、月全体として法定労働時間の範囲内に収めることができます。
この制度を導入するには、就業規則への記載又は労使協定の締結(監督署届出)が必要です。また、労働者にとって不利益とならないよう、あらかじめ労働日や労働時間のスケジュールを明示することが求められます。
なお、1カ月単位の変形労働時間制を導入していても、法定休日は必ず暦日で週1回以上確保する必要があります。そのため、スケジュールを作成する際には、法定休日が暦日単位で設定されているか、また週1回以上確保されているかを必ずご確認ください。
以上のように、法定休日と法定外休日の違いを正しく理解し、法定休日は暦日で与える必要があることを踏まえたうえで、1カ月単位の変形労働時間制を適切に運用することが大切です。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。